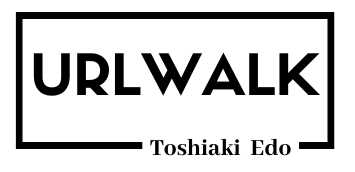糖尿病予防には、実践計画を立てることが不可欠ではないでしょうか。実は、健康診断で高血圧や糖尿病を疑われるような数値結果ができました。そして、地域の自治体から栄養指導を兼ねた生活習慣病予防の勉強会参加を余儀なくされました。私は、健康のため数回に分けて開催されたセミナーに参加しました。
私は、参加したセミナーでメモを取り、備忘録として記録を残しておこうと判断しました。その方法がこのサイト記事にすることです。糖尿病予防のための実践計画は、健康な体を維持し、糖尿病を予防するための具体的な目標と工夫をまとめたものです。日々の生活に取り入れやすい「食事」「運動」「基礎知識」の3つの柱で構成されています。
柱1:毎日の食習慣を見直す
毎日の食習慣を見直すことは、血糖値のコントロールと適正体重の維持を目指し、食事の量と質を改善します。
1. 摂取量の目標設定
| 項目 | 目標 | ポイント |
| 目標体重 | 例:身長 160㎝ の場合 50㎏~ 55 ㎏を目指す | 肥満の解消・予防は予防の基本です。現在の体重を毎日記録しましょう。 |
| エネルギー量 | 1日1500kcal1600kcalを目安 | 過食を避け、適切なカロリーを心がけます。 |
| 主食(ご飯) | 1日1合程度(320g)に抑える | 大盛りでの摂取を避け、炭水化物(糖質)の摂り過ぎに注意します。 |
2. 栄養バランスと食べる工夫
栄養バランスを考えた取り組みは、食べる工夫で整えられます。
野菜の積極的摂取
健康な身体を目指すには、毎食、野菜を摂ることが大事です。目安としては、野菜摂取1日小皿5杯分(目標350g)を目指します。また、野菜を先に食べることで、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。
良質なたんぱく質と脂質
食習慣の見直しでは、良質なたんぱく質の摂取や良質な脂質の摂取が求められます。たんぱく質は筋肉や肝臓の材料になります。刺身、半熟玉子、納豆など、動物性と植物性のバランスを意識して摂取しましょう。脂質は、青魚に多く含まれるDHAやEPA(omega3脂肪酸)を積極的に摂り、油の摂り過ぎ(揚げ物など)を控えます。
消化に良いものを食べる
消化に良いものは、胃腸にやさしく内蔵に負担を掛けないという目的としても重要です。胃腸に負担の少ない食事を心がけましょう。
炭水化物(糖質)の認識
ご飯やパン、麺、芋、豆類には炭水化物(糖質)が多く含まれます。糖は体内でブドウ糖に分解され、肝臓に貯蔵されるため、過剰摂取に注意が必要です。ここが大きなポイントですね。注意をしなければなりません。
献立の例
朝食はパン、梨、くるみなど、バランスの取れた組み合わせを意識します。くるみなどが良いとは思いませんでした。
3. アルコール(飲酒)3つのルール
- 飲酒は休肝日を設けます。
- 1日の適量は純アルコール量として20g~25g程度まで(例:ビール 500ml缶1本)
- ビールや日本酒など、糖質が多く含まれる酒類の飲み過ぎに特に注意しましょう。
柱2:適度な運動を生活に取り入れる
運動は、筋肉をつくり、血糖を消費し、脂肪燃焼を促すために不可欠です。適度な運動を生活に取り入れることが必要。
運動の目標と頻度
-
- 有酸素運動: 1日20分〜 30分程度の有酸素運動を目標とします。
- 実施頻度: 今月は週3回の実施を目指して習慣化しましょう。
運動のタイミングと工夫
運動のタイミングと工夫は、以下の点がポイントになります。
食後の運動
運動は食後に行うと、血糖吸収を緩やかにする効果が期待できます。
座る時間を減らす
1日1時間以上座っている人は、10分毎に行動し、こまめに体を動かすことを意識しましょう。
筋肉づくり
血糖を効率よく消費するために、たんぱく質をしっかり摂りながら筋肉をつくるトレーニングを取り入れましょう。
具体的な運動の例
ラジオ体操、ストレッチ、散歩などを日常生活に取り入れ、運動不足を解消します。
柱3:生活全般の基礎知識
生活全般において、糖尿病予防の基礎知識は以下の取り組みが大事だと教えていただきました。
睡眠
睡眠は、疲労回復とホルモンバランスのため、重要です。良質な睡眠をしっかりとりましょう。
継続的な記録
食べたものや体重、運動を記録することで、自身の生活習慣を「全て普通にできているか」客観的に把握し、計画の見直しに役立てましょう。
この計画を無理なく継続することが、糖尿病予防への最も重要な一歩となります。